煎りぬか(いりぬか)の作り方というと難しいイメージがあるかもしれませんね。
でも実際に作ってみると驚くほど簡単です。
煎りぬかの作り方のちょっとしたコツや保存方法もしっかりと押さえましょう。
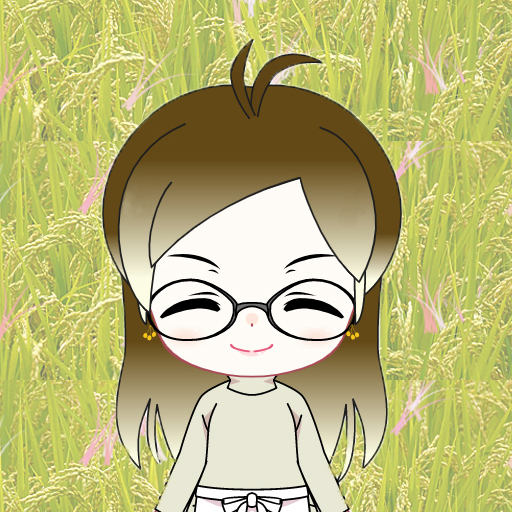
炒りぬかの使い方の幅がどんどん広がりますよ。

煎りぬかの作り方、あなたもぜひマスターしてくださいにゃん。
動画でご覧になりたい場合はこちらをどうぞ↓
では早速参りましょう。
煎りぬかの作り方・準備

煎りぬか(いりぬか)の基本的な作り方をご紹介します。
まずは、下記の通り、材料の米ぬかと用意するものを準備してください。
材料
米ぬか:適量
出来る限り新鮮な米ぬかを使いましょう。
また、食用の米ぬかには無農薬や減農薬、有機農法の米ぬかを選んでください。
例えば、こちらの米ぬかなら無農薬で安心です。
私も購入しています♪
量は多めですが、たっぷりと使えるのでおすすめです↓
用意するもの
- フライパン又は鍋
- ヘラ
- 保存容器(使う頻度によって決めるのがおすすめ)
フライパンは、他の鍋で代用しても大丈夫です。
米ぬかを煎る工程は、どちらかというとフライパンの方が簡単です。
でも焦げないように気をつければ、他の鍋でも煎りぬかを作ることができますよ。
ちなみに、私の場合はいつもテフロン加工の小さな片手鍋を使用しています。
そして、保存容器は、煎りぬかを使う頻度にもよりますが、2種類あると便利です。
具体的には、次のように2種類を使い分けています。
- すぐに食べる煎りぬか用:ペットボトル
- すぐに使わない煎りぬか用:チャック付きの保存袋

ペットボトルに入れておくとサッと使えて便利だにゃん♪
続いて、煎りぬかを作る手順を見ていきましょう。
煎りぬかの作り方・手順
- フライパンに米ぬかを入れる
- コンロに火をつける
- 香りが立つまで3~5分煎る
- 香ばしい香りが立ってきたら火を止める
- 十分に冷ます
- 冷めたら保存容器に入れる
1~6の手順通りに作っていきます。
1:フライパンに米ぬかを入れる

冷たい状態のフライパン(鍋)に、生の米ぬかを入れます。
2:コンロに火をつける

コンロに火をつけたら、弱火にします。
米ぬかは油をひかずに煎るので、焦げないように必ず弱火にしましょう。
3:香りが立つまで3~5分煎る

米ぬかが焦げないようにヘラでよくかき混ぜながら3~5分程度煎りましょう。
焦げるのが心配な場合は、ごくごく弱火にして7~8分程度煎ってください。
しばらくすると、米ぬかから甘い香りが立ってきます。
ところで、「煎りぬか」と「炒りぬか」の違いは何だかご存知でしょうか。
実は、ただの漢字の違いだけです。
「炒りぬか」でも間違いではありません。
でも、油をひかずに水分を飛ばすという意味では「煎りぬか」がふさわしい漢字だといえますね。
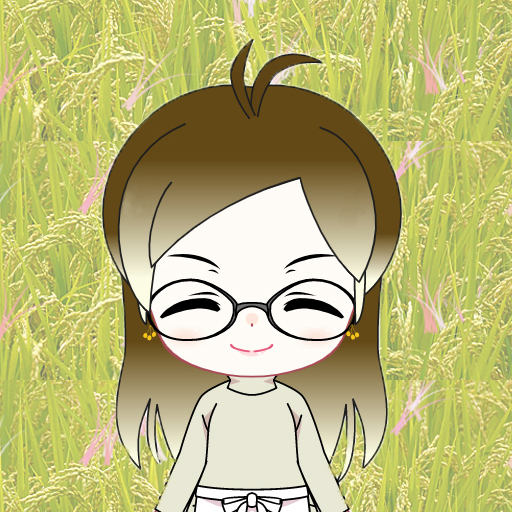
ご参考までに^^
4:香ばしい香りが立ってきたら火を止める

米ぬかが少し色づき、香ばしい香りが立ってきたら火を止めましょう。
この時、火を止めてもヘラで混ぜ続けることが大切です。
5:十分に冷ます

出来上がった煎りぬかは、十分に冷ましましょう。
すぐに保存容器に入れずに、必ず冷ましてくださいね。
6:冷めたら保存容器に入れる
煎りぬかが冷めたら、用意しておいた保存容器に入れます。
煎りぬかの出来上がりです!

米ぬかの作り方って簡単だにゃん。
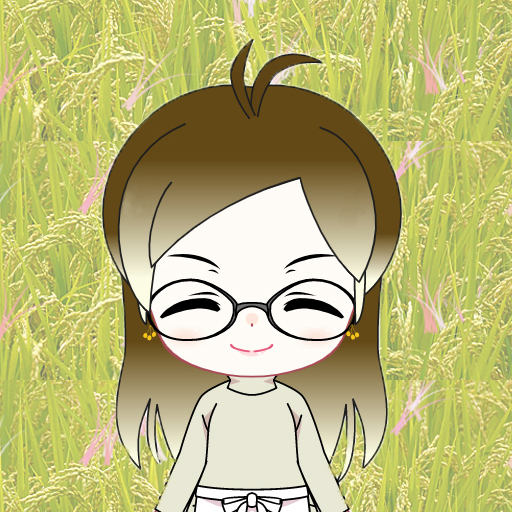
ちょっとしたコツを押さえれば、さらに簡単に作ることができますよ。
続いて、煎りぬかの作り方のコツをご紹介します。
煎りぬかの作り方のコツ
煎りぬかの作り方のコツは、次の3つです。
- 最初は少量から作る
- 弱火でまんべんなく混ぜる
- 甘く香ばしい香りが立って来たら早めに火を止める
煎りぬかは焦げやすいので、最初は少量から作るようにします。
フライパン(鍋)の大きさにもよりますが、大さじ10杯程度を目安にしてください。
生の米ぬかの場合、大さじ10杯で約50gになります。
そして、煎りぬか作りに慣れてきたら、一度に作る量を増やすようにしましょう。
コンロに火をつけたら、弱火のままヘラでまんべんなく混ぜます。
フライパン(鍋)に当たる部分がムラにならないように、こまめに混ぜるのがポイントです。
甘く香ばしい香りが立って来たら、早めに火を止めましょう。
煎りぬかは、油断をするとすぐに黒っぽく焦げるので注意をしてください。
慣れるまでは、少し早めに火を止めるのがおすすめです。
コンロからフライパン(鍋)を外して混ぜると焦げにくいですよ。
3つのコツを押さえれば、美味しい煎りぬかが出来上がります♪
美味しい煎りぬかが出来上がったら、保存方法もしっかりと押さえておきましょう。
煎りぬかの保存方法
煎りぬかの保存方法は、冷蔵保存または冷凍保存です。
できるだけ密封状態で保存容器に入れて保存しましょう。
冷蔵保存なら約1週間、冷凍保存なら約1~2ヶ月保存することができます。
私の場合、煎りぬかはすぐに食べるのでペットボトルに入れて冷蔵庫で保存しています。
もし、煎りぬかをすぐに使わない場合は、チャック付きの保存袋に入れることをおすすめします。
チャック付きの保存袋の方が空気に触れる部分が少なくなります。
米ぬかの保存方法についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。
まとめ

今回は、煎りぬかの作り方をご紹介しました。
食用の米ぬかは、煎りぬかにするのが基本です。
ちょっとしたコツや保存方法もしっかりと押さえて、米ぬかを生活のさまざまな場面で使ってみてくださいね。

早速、作ってみるにゃん。
こちらの米ぬかなら無農薬で安心です。
たっぷりと使えるのでおすすめですよ↓
米ぬかの使い道についてのこちらの記事もおすすめです。